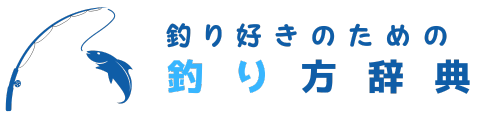イイダコの釣り方



イイダコの特徴と生態について
イイダコは、八腕形目マダコ科マダコ属に分類される小型のタコです。
イイダコは、日本の北海道南部以南の沿岸域から朝鮮半島南部や中国の沿岸に生息しています。
イイダコは体表が低いイボ状の突起で覆われており、茶褐色の体色をしています。
ただし、環境によって体色が変わることもあります。
また、イイダコは興奮すると胴や脚に黒い縦帯模様が現れます。
イイダコの体長は最大で15cmほどで、非常に小型のタコと言えます。
腕の長さはほぼ等長で、吸盤が2列に並んでいます。
マダコの仔に似ていることもありますが、イイダコは脚の付け根の部分に金色の環状紋がふたつあるため、これで区別することができます。
イイダコは水深が10mほどの内湾で、岩礁や石が点在する砂泥底に生息しています。
昼間は石の隙間やアマモ場に潜んでおり、大きな二枚貝の殻や空き瓶などでも見つかることがあります。
そして夜になると海底を移動しながら餌を探し、甲殻類、多毛類、貝類などの底生生物を捕食します。
イイダコは日中でも餌が目の前にあれば積極的に捕食するため、明るい時間帯でもよく釣れることがあります。
イイダコは冬から春にかけて産卵します。
岩の間などには、半透明で長さ4~8mmほどの卵が200~600個ほど産み付けられます。
イイダコの産卵後は、雌が卵を見守り、保護します。
約40~50日で卵は孵化し、ほとんどの雌はその後死んでしまいます。
孵化したばかりの幼体イイダコは1cmほどの大きさで、既に吸盤も備わっており、すぐに底生生活を始めます。
イイダコの寿命は約1年とされています。
イイダコの英名である「ocellated」は日本語で「目のような模様のある」という意味です。
この名前は、イイダコの脚の付け根の模様を指して命名されました。
また、イイダコの和名は二つの説があります。
一つは、イイダコの胴の内部にぎっしり詰まった卵が飯粒のように見えることから、「イイダコ」と呼ばれるようになったとする説です。
もう一つは、イイダコの卵の食感がご飯に似ているため、「イイダコ」と呼ばれるようになったとする説もあります。
イイダコの釣り方と仕掛けの種類
イイダコ釣りとは
東京湾では、船に乗って楽しむことができる釣りの一つがイイダコ釣りです。
全国的には、堤防や海岸での釣りが人気ですが、東京湾では船上からの釣りが主流となっています。
イイダコ釣りに使用する釣り具
イイダコ釣りには、専用の投げ釣り用具であるイイダコテンヤやスッテが使用されます。
スッテを使用する場合、回転性能が優れたローリングスナップサルカンが用いられます。
釣り糸にはオモリ(5~10号)をセットし、それをスッテに取り付けます。
以上のように、イイダコ釣りは東京湾では船上から楽しむことができる一般的な釣りであり、釣り具としては専用の投げ釣り用具やスッテ、スナップサルカンなどが使用されます。
※回答は自由追加出来ます。
| 釣り方辞典 | ||
|---|---|---|
| イソマグロ(磯鮪)の釣り方 | (アカメフグ)ヒガンフグの釣り方 | アラの釣り方 |
| イスズミの釣り方 | イシナギの釣り方 | イシダイの釣り方 |
| イシガレイの釣り方 | イシガキダイの釣り方 | イサキの釣り方 |
| イイダコの釣り方 | アナゴの釣り方 | アマダイの釣り方 |
| アジの釣り方 | アコウダイの釣り方 | アカムツの釣り方 |
| アカハタの釣り方 | アカエイの釣り方 | アオチビキの釣り方 |
| アイナメの釣り方 | アイゴの釣り方 |