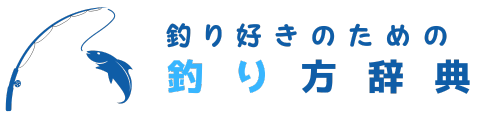アマダイの釣り方



アマダイの生息地と繁殖行動
アマダイは、アマダイ科に属し、主にインド太平洋の大陸棚に生息している海水魚の総称です。
日本でも、アカアマダイ、シロアマダイ、キアマダイなどの種類が存在し、特にアカアマダイは重要な食用魚として知られています。
アマダイの特徴的な姿勢は、体が前後に細長く側扁していることです。
また、頭部は額とアゴが角ばっており、「屈頭魚」という名もあります。
そのため、関西地方では「クジ」とか「グジ」と呼ばれ、中国では「馬頭魚」とも呼ばれています。
さらに、英語では「Horsehead tilefish」とも呼ばれています。
アカアマダイは、赤みがかった体色と、くさび形の銀白色の斑紋が特徴です。
一方、「シロアマダイ」は体の色が白っぽく、「シラカワ」とも呼ばれています。
「キアマダイ」は背ビレと尾ビレが黄色がかっており、目の下縁から上アゴに走る銀白線が特徴です。
特にアカアマダイは釣りの主要な対象魚となっており、漁獲量も多いです。
成魚の体長は最大で60cmほどになります。
アカアマダイは、岩礁と砂泥底が混じった水深30〜150mの場所に巣穴を作る習性があります。
彼らは体を潜らせたり、巣穴に隠れたりして生活します。
なお、アカアマダイの巣穴は、集団で形成されることもあり、その範囲は直径200m前後にも及ぶことがあります。
アカアマダイは、非常に強い縄張り意識を持っており、他のアカアマダイが縄張りに侵入してくる場合は、体当たりして追い払うことが知られています。
アカアマダイの生態と特徴
アカアマダイは、昼間は巣穴から出て餌を捕食し、夜には巣穴に戻る生活をしています。
産卵期は9〜12月であり、この時期には水深70〜100mの海底で産卵を行います。
孵化した稚魚は、大きな目を持ちながらも水深10〜50mの層を浮遊します。
そして、体長が3mmに達すると、突起や微小棘が消え、約3cmまで成長すると海底に下りて底生生活を始めます。
アカアマダイの成長は非常に早く、たった1年で17cm、2年で22cm、3年で25cm、4年で30cmになるという特徴があります。
彼らは肉食性であり、海底に生息するシャコ、エビ、カニ、貝、ヒトデ、ゴカイなどの生物を捕食します。
捕食する際には、逆立ちして餌を探す様子も観察されています。
アカアマダイの個体数は、成長段階によってオスとメスの割合が異なります。
体長が25cm以下の個体ではメスの割合が多く、成長するにつれてオスの割合が増えます。
そして、成長し切った30cm以上の大型個体はすべてオスとなり、性転換をする魚と考えられています。
アカアマダイは様々な別名を持っており、島根県では「コビル」とも呼ばれています。
この名前は、アカアマダイが他の「タイ」という魚に比べて大きくならないことに由来しています。
また、古い書物では「屈頭魚」とも書かれており、この名前は彼ら独特の頭の形状に由来しています。
さらに有名な別名としては「オキツダイ」があります。
この名前は、徳川家康の奥女中である興津局が、里帰りの土産として家康にアカアマダイの生干しを献上したことからきています。
家康がこの魚を非常に気に入り、「この魚を興津鯛と呼ぶことにしましょう」と言ったため、この魚の名前は興津鯛と呼ばれるようになったのです。
アカアマダイの釣り方と仕掛けについて詳しく解説
若狭湾は、アカアマダイの生息地として有名です。
福井県漁業連合は、アカアマダイのブランド化を推進しており、その高品質なアカアマダイは評価されています。
アカアマダイの釣りは、手漕ぎボートでの釣りが盛んな地域では手漕ぎボートを利用することもできますが、一般的には乗合船を利用することが人気です。
関東地域では、相模湾沿岸で専門の大型乗合船を利用してアカアマダイを釣ることができます。
釣り方としては、船釣りで用いる片テンビン仕掛けを使用し、魚を狙いながら定期的に誘いを入れます。
竿には、アカアマダイに適した柔軟な穂先としっかりとした胴のビシ竿や専用のアマダイ竿を使用することがおすすめです。
竿の長さは2.1〜2.7メートル、オモリの負荷は30〜50号を目安に選びましょう。
仕掛けは片テンビンで、針にオキアミなどのエサをつけただけの簡単なものです。
また、ハリの下部に夜光玉を付けることで、エサをより目立たせることができます。
主にオキアミを使用しますが、状況によってはイワイソメも有効です。
仕掛けを水中に投入した後、オモリを底に着底させ、約1メートルほど底を切ります。
そして、魚が食いついたことを示すアタリを待ちます。
底近くで仕掛けを漂わせたいため、海底に変化がある場合は定期的に底を取り直す必要があります。
また、竿をゆっくりと上下させることで魚を誘い出すことも重要です。
明確なアタリがあったら、軽く竿を立ててハリをしっかりとかけましょう。
浅場での釣りでは、ライトゲームを楽しむこともできます。
この場合、専用のライトゲームロッドを使用し、PEラインの1〜1.5号を使うことがおすすめです。
また、5号程度の先イトを結んでおくことも有効です。
アカアマダイを釣る際には、上記の仕掛けや釣り方を試してみてください。
楽しい釣りができること間違いありません。
若狭湾でのアカアマダイ釣りの楽しみ方とポイント
若狭湾でのアカアマダイ釣りは、忍耐と技術を要する釣りの一つですが、特に楽しみながら充実感を得ることができます。
ぜひ若狭湾で素晴らしい釣り体験をしてみてください。
以下では、ライトゲームの釣り方のポイントをご紹介します。
ライトゲームの釣り方のポイント
ライトゲームは、興奮が味わえる釣り方ですが、大型の魚に備えるためには、ドラグを緩めに設定しておくことが重要です。
船釣りの場合、地域や船長によってはビシ釣りが行われます。
ビシ釣りは、マダイと一緒に釣りを楽しむことができる釣り方です。
通常、ビシ竿の50号クラスと中型の両軸リールを使用します。
深い場所を狙うため、電動式のリールを使用しても良いでしょう。
また、エサ取りが少ない場合は、夜行玉を取り外しておくこともあります。
付けエサには、オキアミかイワイソメが使用されます。
オキアミは尾羽をカットして一匹を掛け、イワイソメは約5cmの長さで通し刺しにします。
釣り方は、底をしっかりと探り、竿を約1m上げた位置でコマセを振り出すようにします。
エサ取りが多いため、定期的に付けエサの状態を確認してください。
船釣りの場合、アマダイはゆっくりとリーリングするだけで、竿先が十分に絞り込まれてから掛かってくることが多いので、問題ありません。
胴付き仕掛けの場合、長崎の潟釣りでは大型のアマダイを狙います。
この仕掛けは、幹糸に2本のハリスを枝状に出し、先端にオモリを付けるため、タナ取りは簡単です。
ただし、枝状の部分が長いと幹糸と絡んでしまうので、約50cmに短くしておくことが必要です。
付けエサには、活きエビの他にもオキアミやイワイソメ、イカなどを使用することもあります。
イカを使う場合は、約7mmの幅と約6cmの長さに薄く仕上げてハリに乗せます。
釣りのポイント
魚がエサに食いついた兆候が見られ、竿がアタリを感じた場合は、素早くアワセを入れましょう。
アワセとは、釣り針を魚の口に確実に引っ掛けるために竿を引く動作のことを指します。
このアワセを入れることによって、魚がしっかりと釣り針に引っ掛かり、逃げ出すことを防ぐことができます。
しかし、アワセのタイミングが遅いと、魚がエサを食べた瞬間に逃げ出してしまう可能性があるため、注意が必要です。
ですから、魚がエサに食いついた兆候が見られたら、なるべく早くアワセを入れるようにしましょう。
また、アワセを入れる際は、素早く正確に竿を引く必要があります。
力を抜きすぎたり、強く引いたりすると針が外れてしまう可能性があるため、適切な力加減で行うことが重要です。
アワセのタイミングや力加減は、経験と感覚を駆使して身につけるものです。
上達するには、実際に釣りをして状況に応じてアワセを入れる練習を積むことが必要です。
慣れるまでは失敗もあるかもしれませんが、継続してトライすることで上達していけるでしょう。
アワセは、釣りの楽しみをさらに引き立てる重要な要素であり、釣果にも大きく影響を与えます。
正しいタイミングでアワセを入れ、上手に釣りを楽しんでください。
※回答は自由追加出来ます。
| 釣り方辞典 | ||
|---|---|---|
| イソマグロ(磯鮪)の釣り方 | (アカメフグ)ヒガンフグの釣り方 | アラの釣り方 |
| イスズミの釣り方 | イシナギの釣り方 | イシダイの釣り方 |
| イシガレイの釣り方 | イシガキダイの釣り方 | イサキの釣り方 |
| イイダコの釣り方 | アナゴの釣り方 | アマダイの釣り方 |
| アジの釣り方 | アコウダイの釣り方 | アカムツの釣り方 |
| アカハタの釣り方 | アカエイの釣り方 | アオチビキの釣り方 |
| アイナメの釣り方 | アイゴの釣り方 |